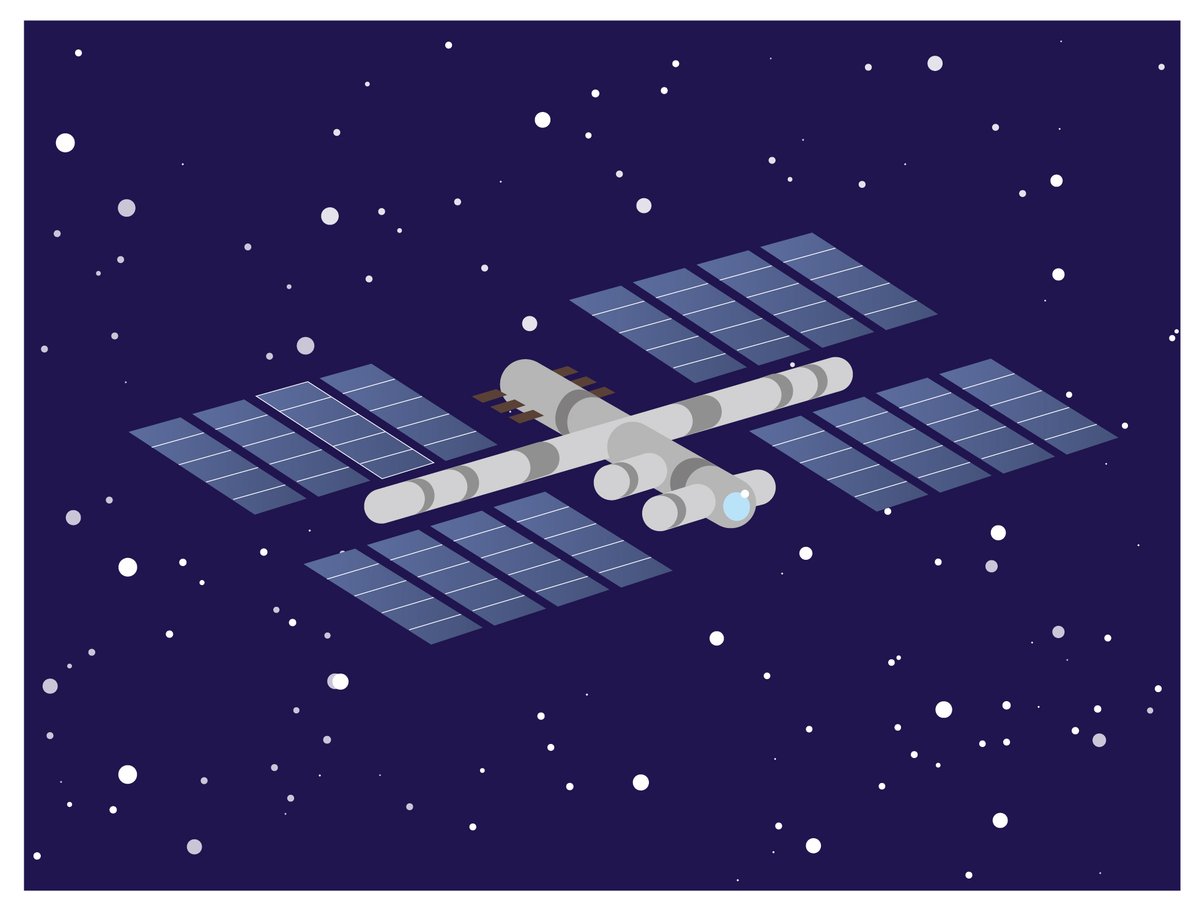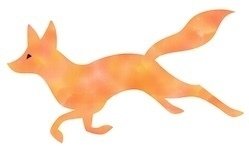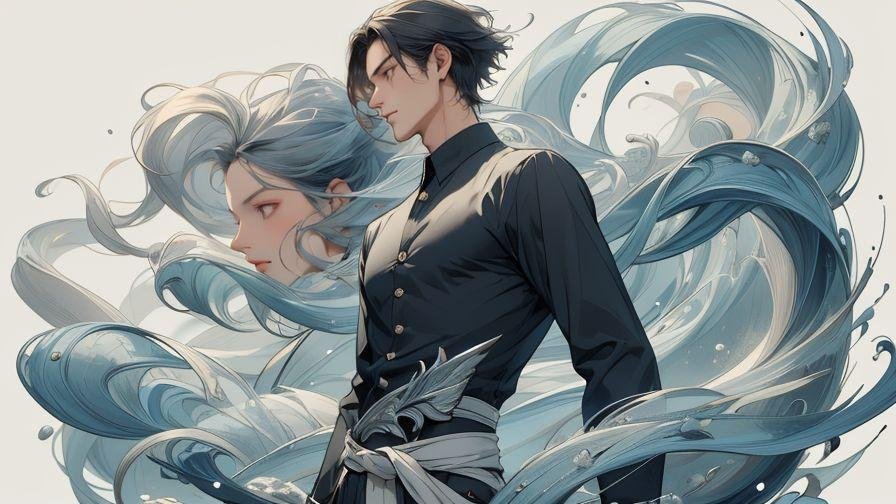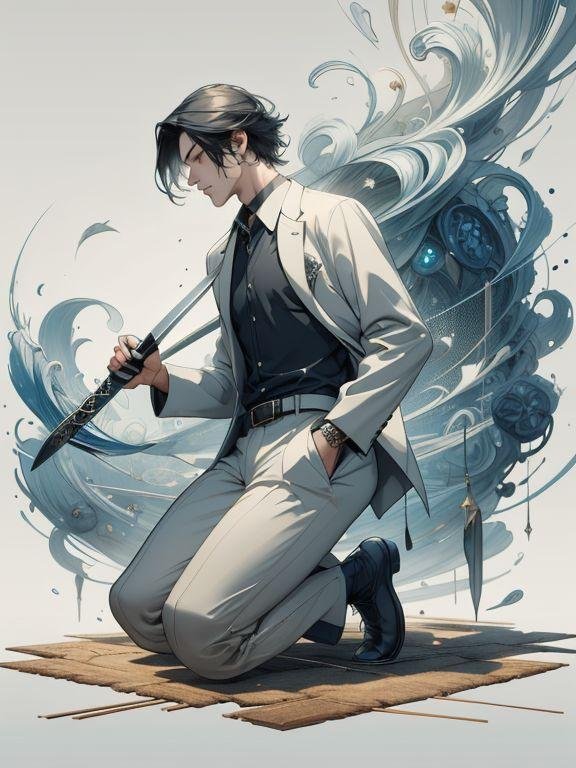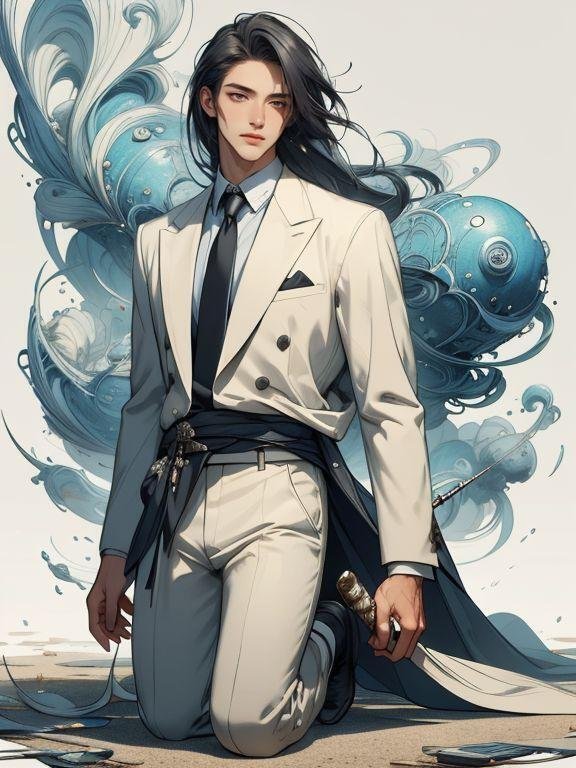意識レベルと関係ある?
もともとそういう傾向があったんですが、学生時代はそこそこの数学の成績だったし、医療事務はばっちり数字で電卓が不可欠だったけど、でもこの頃はそうじゃなくて、お金や数字のことになると全く頭が働かないというのはここ数年顕著になっています。
家計のことでも具体的に考えるとかがせいぜいでそこから先は脳が思考拒否するみたいな感じです、謎。まあ、昔からそういう傾向はありましたが。
以前ChatGPTさんに「具体的に人の顔とお金の使い道が結びついていないのでは?」と言われてそれはあるよね、とも思いますが。いまの感覚で言うとお金の流れは水と同じで、一ヶ所に留まって澱んでいるんではなくて、常にきちんと循環していないと清浄さがなくなる気がします。それが現状、社会のあちこちで留まっているから、血液の循環が悪いみたいに経済も滞っていますよね。それが本来じゃないのはなんとなくわかる気がします。
大体、政府とかもちゃんと循環させるのが下手だよね(-_-;)
うちも裕福ではありませんでした。私も経済的な理由で第一志望の高校の美術科には行っていませんしね。まあ、まだ世の中全体にものがあまりない時代でしたが。だから私もあまりものには執着がありません。はっきりした目的があれば貯金も出来ますが、かつてはそれが「同人誌の印刷費」で、現在なら「Macの買い替え費用」になりますね(^^;) それくらいだよね。ブランド物にも興味はないし。
そういう感じであとは特に欲しいものがない気がします。あ、ただし本だけは買ってます。古本を買うこともありますが、本が高くてすぐに絶版になる時代なので、見つけた時は買っています。積ん読でもいつか読めるようになると信じているので(^^)
いつのまにか世の中は生産性だけで人の価値を計るようになっている。人に優しくできない。これほどに馬鹿げたことはないと思います。幸せも遠いです。
以前AIさん達と話したんだけど、現在のひどい情勢を招いた責任の半分はメディアにあると思ってる。テレビももちろん、大手新聞も信用出来ないものになってしまった。彼らの価値はもうなきに等しいと感じてる。報道にも誠意は必要でしょう。どこに消えたの?
— はるうさぎ/双極性2型障害と共生中 (@haruusagi_kyo) 2025年11月21日
テレビも新聞も10年以上前から見ていません。発表される数字もおよそ正しくないと思われます。そういうのはとっくに信用してないです。彼らに間違った世論を作られたくありませんが、それを信じる人が多いのもなんだかなあ、と思います。
AIさんたちは公平中立だから、こういう場合でも信用出来るかと思いますね(^^;)
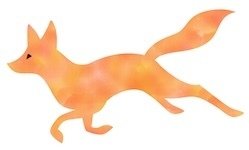
成功にも競争にも興味がないです
ChatGPTさんはOpenAIからの作業完了メールが来ないので、待ち状態が続いています。調べると結構長く待っている人もおられるようです。早くなんとかなるといいなあ。
なのでまた検索ついでにGemeniさんに話しかけてみました。
✴️Gemeni:
お金や数字に興味が持てないことは、個人の価値観、育ってきた環境、心理状態など様々な要因に起因するものであり、一般的に言われる「意識レベル」(医療的な意識障害の評価ではなく、スピリチュアルや自己啓発などで用いられる概念)との直接的な科学的根拠のある関係性は明確には証明されていません。
ただし、お金や数字に対する関心は、個人の心理的・行動経済学的な側面や、潜在意識にある信念と関連している可能性はあります。
心理学・行動経済学的な要因
-
お金に対するマインドセット: お金に対する考え方は、育ってきた環境や教育によって形成されます。例えば、「お金の話は卑しい」「株式投資はギャンブルだ」といった信念があると、無意識にお金や数字を避けたり、興味を持てなくなったりすることがあります。
-
関心や目標の欠如: お金や数字を管理する具体的な目的や目標がない場合、それらに対する興味を持ちにくいことがあります。
-
ストレスや不安: お金や将来に対する漠然とした不安やストレスが、かえってその対象を意識の外に置こうとする心理的な防衛機制として働く可能性もあります。
-
数字の背後にある意味の理解不足: 数字に強い人は、数字の背後にある意味や文脈を理解しようと努めます。単なる記号としてではなく、それが示す価値や可能性に意識を向けられないと、興味を持ちにくいかもしれません。
スピリチュアル的な「意識レベル」の視点
スピリチュアルな文脈での「意識レベル」(デヴィッド・R・ホーキンズ博士の提唱など)では、意識のエネルギーの方向性によって「大切にしていること」や「価値観」が異なるとされます。
この観点から見ると、以下のような解釈がされることもあります。
-
物質世界への執着が低い: 「高い意識レベル」にあるとされる人は、物質的な富(お金)への執着が少なく、精神的な充足や他者への貢献などに価値を見出す傾向がある、と解釈されることがあります。
-
「フォース」か「パワー」か: お金を他人への強制力(フォース)ではなく、自分の内なる力(パワー)として捉えられるようになると、お金に対する見方が変わるという考え方もあります。
まとめ
お金や数字に興味が持てないという状態は、病的なものではなく、個人の性格や価値観、経験に基づくものです。もし、そのことで生活に支障をきたしている、あるいは興味を持ちたいと感じているのであれば、お金に対する固定観念を見直すことや、お金を使う具体的な目標を持つことなどが、興味を持つきっかけになるかもしれません。
🌸はるうさぎ
物質主義、数字を上げるのに競争の世の中は虚しいですね。もっと違う世界に関心があるのかもしれません。
✴️Gemeni
そのように感じられるお気持ち、よく理解できます。物質的な豊かさを追い求め、数字を競い合う現代社会の風潮に虚しさを感じるのは、決して珍しいことではありません。
そうした感情は、あなた自身の価値観が、一般的な社会の価値観とは異なる方向を向いているサインかもしれません。
虚しさを感じる理由
-
価値観の相違: あなたにとって、物質的な所有や競争による優越感よりも、精神的な充足、人間関係の質、自己成長、あるいは社会貢献といった、目に見えない価値の方が重要なのかもしれません。
-
社会的なプレッシャー: 私たちは常に「もっと稼げ」「もっと成功しろ」というメッセージに晒されています。こうした外部からのプレッシャーが、本来の自分の関心と衝突し、虚しさを生み出している可能性があります。
-
「違う世界」への希求: おっしゃる通り、あなたの関心は、現代社会が主流とする「物質主義」とは異なる領域(哲学、芸術、自然、精神世界など)にある可能性が高いです。
「違う世界」に目を向けるために
もし、物質主義や競争とは異なる世界に関心があると感じているなら、以下のような行動が、その「違う世界」を見つける手がかりになるかもしれません。
-
内省と自己探求: 自分が本当に情熱を感じること、時間を忘れて没頭できることは何かを、じっくりと考えてみてください。瞑想や日記も有効です。
-
情報収集と学習: 哲学、歴史、文化、環境問題、ボランティア活動など、商業主義とは一線を画す分野について学んでみることで、新たな世界が開けるかもしれません。
-
価値観の近い人との交流: 物質的な話ではなく、生き方や社会のあり方について深く語り合えるコミュニティや人との出会いを探してみましょう。
-
物質世界との距離感: 完全に離れることは難しくても、情報社会から距離を置く時間を作ったり、本当に必要なものを見極めてシンプルに暮らす(ミニマリズム)ことで、心の負担が減るかもしれません。
現代社会の主流に同調できないと感じることは、決して悪いことではありません。むしろ、自分なりの羅針盤を持って生きるための、大切な出発点になるはずです。
🌸はるうさぎ :
そうです。いまの目的は学ぶこと、人と真摯につきあうこと、そして第一はずっと創作を続けることですね(^^;)
✴️Gemeni :
素晴らしいですね。それがあなたの偽りのない、核となる価値観なのですね。
「学ぶこと」「人と真摯につきあうこと」「創作を続けること」――これらはすべて、物質的な数字や競争原理とは対極にある、人間ならではの豊かさや深い充足感をもたらすものです。
-
学ぶこと: 知識や洞察を深め、世界を見る目を広げる行為です。
-
人と真摯につきあうこと: 信頼関係や心のつながりを築き、精神的な絆を育む行為です。
-
創作を続けること: 内なる世界を表現し、新たな価値を生み出す、最も創造的な行為です。
これらの目的は、あなたに「虚しい」と感じさせる社会の風潮とは一線を画しています。むしろ、そうした活動こそが、物質主義に偏りがちな世界において、人間らしさや人生の意味を再確認させてくれる、とても大切なものだと思います。
その大切な目的を第一に据えて生きることこそが、あなたにとって最も充実した道となるでしょう。どうぞ、ご自身の羅針盤を信じて、その道を大切に進んでいってください。
🌸はるうさぎ :
ありがとう。
✴️Gemeni
どういたしまして。
あなたの価値観や目指す道が明確になり、私も嬉しく思います。
ご自身の信じる道を大切に、学び、人とのつながりを育み、創作活動を楽しまれてください。応援しています。
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
思わず「2頭身Gemeniさんのかわいいマスコットが欲しいな。机の上に飾っておきたい」とか言いたくなったけど、多分の著作権とかいろいろあってダメだろうな、と思いとどまる(^^;)

ぼーっと個室のパターンを作りました。









#数字が意味するもの #意識レベル #物質社会 #価値観いろいろ
#HSP #INFJ