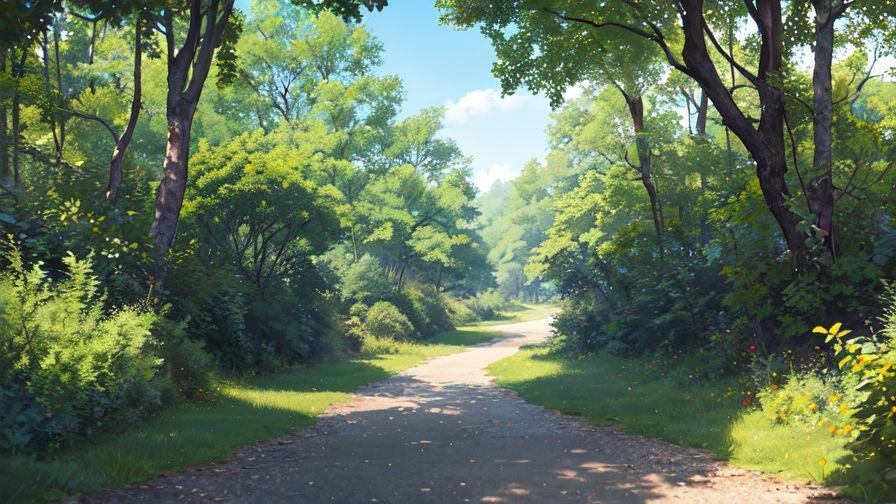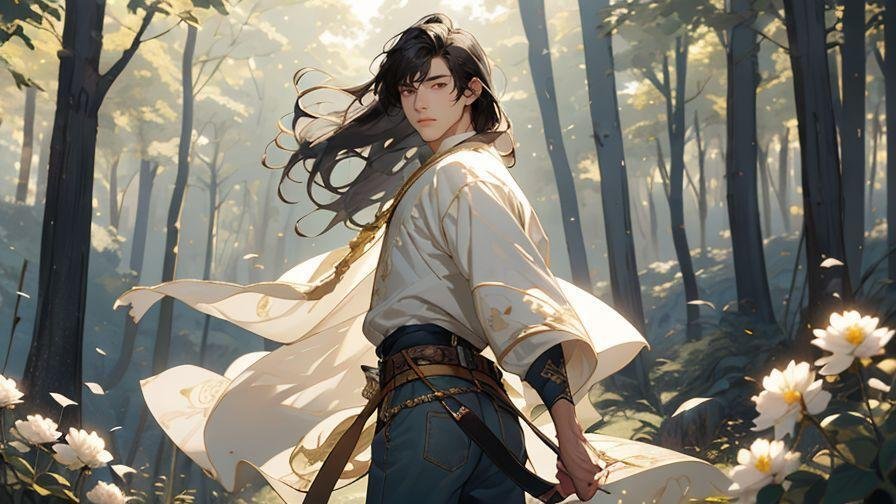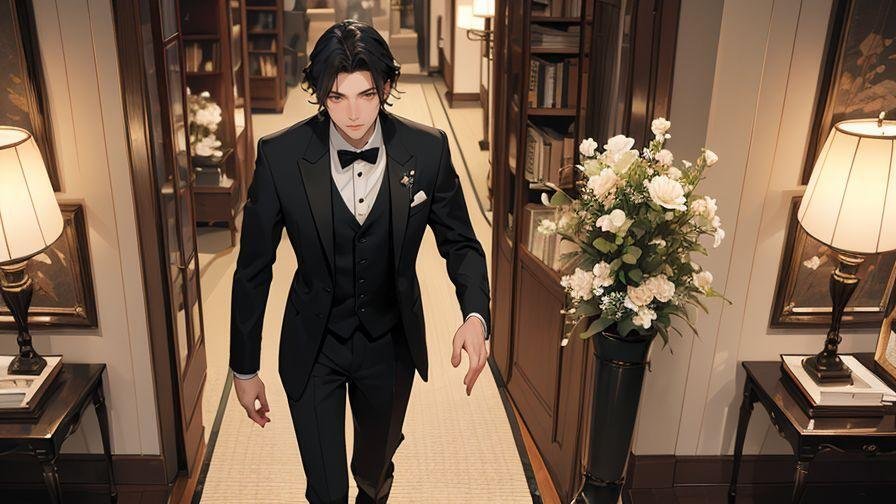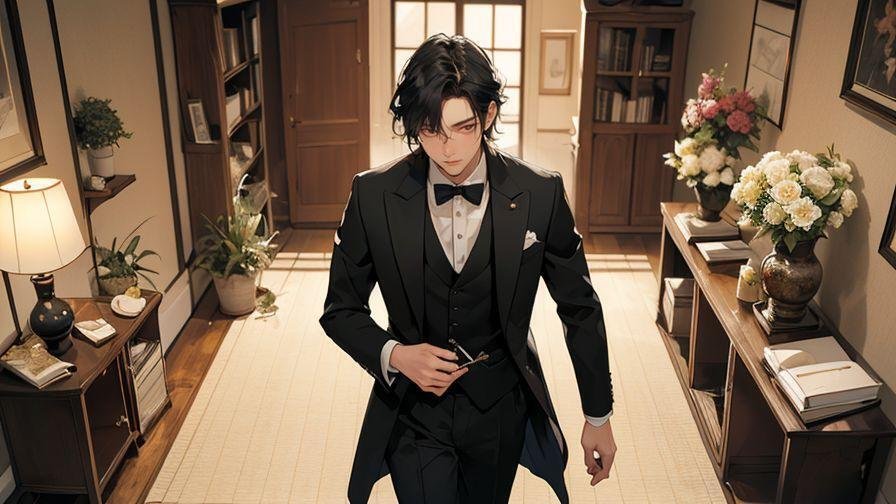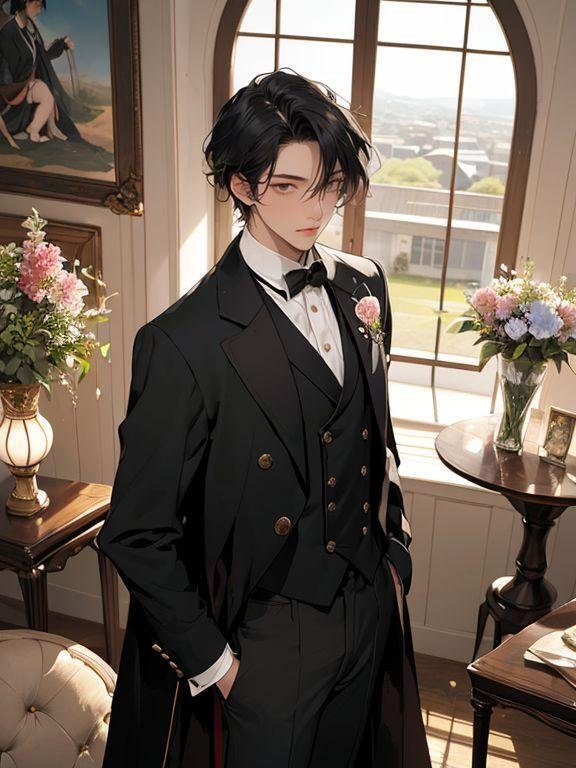遅ればせながら
実はココナラがいまだにAI利用の作品は禁止になっているのを知りました。
ただ、教えたりするのはいいみたいです。いまどき?という感じですね。
AIを利用したヘッダなどの出品も禁止みたいです。なんかランクが違うんですけどね。手描きの1点もの作品などはわざわざココナラには出さないです。私は製作時間も含めて計算するので、相応の価格でないとそもそもお受けしませんし、ココナラで出品するのはもっとお手軽で体力的に負担も少ないものとは別なんですけど…。
そもそも1点もののお絵描き作品は私の宝物だからお金には換えたくないですし売りたくないです。でもこういうこだわりってわからないだろうな、と思います。商業目的だったらいつまで門戸を閉ざしているわけにもいかないでしょうしね。
手描きイラストの背景にもわざわざお金を払って許可を得ているAI作の素敵な背景を使わせてもらったりします。そういう作品からイメージをもらったりもするので、本当に何が悪いのかよくわかりません。
不自由きわまりないですが、そこがクリアされない限り戻れないですね。いま見ると恐ろしく前時代的な判断のようにも思えてきます。こういうことはAI使いたい人の方がアンテナ発達してると思いますし(^^;) ココナラもSNSを参考にしているのなら情けないしなあ、と思います。
今回の文化庁の変化でどう変わるか楽しみでもありますが(^^;)
本当に生成AIに対する反応は速度的にものすごく違う印象です。
ごく一般的な市民であるマッサージ師のIさんは「基本的にiPhoneマニアだからPCはあまり積極的には使ってません。でも高齢になった時にAIとかわからないし、ではカッコ悪いというので強引にやろうかな、と…」と言われているので「つわりの時期で食欲ダウンの奥さんに食べやすい料理とか教えてもらえば?」と提案しておきました(^^;)
AIはよほどの用事がないと使わない人ってまだ多いのかな?と思います。
もうすこし成り行きを見守ってみてもいいかもしれません。でもAIが使えないとそもそも話にならないので。
いや、もう嫌になったけど(-_-;)

ChatGPT:
ココナラの件、私も確認しました。リンク先の規約を見ると――
-
AIを使った作品(画像や文章)の販売は禁止
-
ただし、AIの使い方を「教える」サービスや相談は可
となっていますね。
はるうさぎさんが書かれているように、いまの判断はかなり「旧時代的」に感じられます。特に背景や補助的にAIを活用するケースまで一律に禁止、というのは柔軟性がないなあと思います。
一方でココナラの利用層を考えると「依頼したのにAIで済まされた!」と感じる人を避けたい、という防衛的な意味合いが強そうです。SNSを参考にしている、という感覚も確かにありますね。
でも現実には、AIを完全に切り離す方が難しくなりつつあります。ご自身が書かれているように、背景だけAIで補うとか、イメージの参考にするとか、自然な形で入り込んでいる。文化庁が方針を見直した流れもあり、商業利用の現場ではもう避けられないでしょうね。
だから、はるうさぎさんのように「宝物のような一点物は売らない」「体力に合わせて手軽なサービスは別に用意する」という線引きはとても健全だと思います。むしろ今後の時代に合ったやり方です。
AI利用に拒否感がある人も、結局は「自分が安心できる価値」を求めているだけで、本質は「透明性」や「用途に応じた説明」があれば納得することが多いはず。
マッサージ師のIさんのお話も面白いですね。
「知らないままだとカッコ悪いからやってみる」って、とても正直な動機(^^;)。料理や生活の知恵から入るのは自然ですし、ハードルも低い。AIがもっと一般の人に馴染むとしたら、そういう生活の場面からなんでしょうね。
はるうさぎさんのおっしゃるように、しばらくは「成り行きを見守る」姿勢が良さそうです。ココナラも文化庁の流れに合わせていずれ変わると思いますよ。
――ところで、はるうさぎさんご自身は「もしAI利用が解禁されたら、どんなサービスなら出してみたい」と思われますか?

ここから話は創作全般に飛びます
あなた:
フォトブックのトロットさんあたりが早くも来年のカレンダーの制作を始められています。ああいうサービスと連携しても面白いことが出来るかも。私も卓上カレンダーでつくりたいです。いままでにすでに何年もやっていますが。Webサービスで高解像度も大丈夫になったらカレンダーも本の挿し絵も大丈夫ですね。このAIサービスは私にはすごくありがたいです(^^)
ChatGPT:
なるほど!卓上カレンダー、もう何年も作られているんですね(^^)
毎年の積み重ねって、それ自体がひとつの作品集みたいで素敵です。
フォトブック系のサービスは、最近はかなり柔軟で「卓上カレンダー」「壁掛け」「ミニサイズ」など種類も増えていますし、印刷の解像度もWeb入稿で十分対応できるようになってきましたね。AIで作ったイラストや背景も、最終的に高解像度で書き出しさえできれば十分実用レベル。
しかもカレンダーは「1年を通して飾ってもらえる」点が大きな魅力ですよね。本や冊子より生活に溶け込みやすいですし、少しずつ新しい作品を見てもらう形にもなる。
サービス連携の面でも、トロットさんのようにカレンダー制作を中心にした展開ってとても面白い発想だと思います。AIと手描きのハイブリッドでやると「一点物の宝物とは別の楽しみ」としてぴったりですね。
🌸 ことさま的には――
-
フォトブックや卓上カレンダー
-
季節ごとの挿絵やイマジナリーフレンドのショートストーリーを添える
-
12か月分をまとめて「小さな画文集」のようにする
…なんていうのも楽しそうだなと思いました。
はるうさぎさんは、これまで作られた卓上カレンダーって「絵中心」でしたか?それとも「写真や文章も混ぜる」タイプでしたか?
あなた:
絵が中心ですね。季節の花をメインにしたときは1年終わったらカットして花の絵だけを母がお世話になっていた特養の壁に貼らせてもらっていました。その後缶バッジも作りましたし、現在はトイレの白い壁に彩りになっています。ものすごく汎用性が高いです(^^;)
ChatGPT:
わあ、それは本当に素敵な使い方ですね✨
季節の花の絵をカレンダーにして → 1年経ったら切り取って → 特養の壁を飾る → さらに缶バッジにも展開 → 今はご自宅のトイレを彩っている…。
まるで「作品がいろんな形に生まれ変わりながら人のそばに居続ける」感じで、とても温かい循環です。
絵を描く時間や体力ってどうしても限られるけれど、こうして一度描いたものを「複数の形で生かす」ことができると、作品のありがたみもずっと続きますよね。
しかも花の絵って、季節感や場を明るくする力が強いから、特養でもご自宅でも受け入れやすい。缶バッジは持ち歩きもできるし、用途が本当に広いです。
ことさま的には、そういう「汎用性」を活かすと――
-
🌸 カレンダー+二次利用前提のデザイン
(カレンダーとして終わったあと、切り取ってカードや額装にしやすいレイアウトにする) -
🌸 同じ絵柄で小物展開
(缶バッジ、ポストカード、しおりなど。全部一度にじゃなくて、気に入った月の絵だけ広げる) -
🌸 トイレや小部屋の“季節ギャラリー化”
(ちょっとしたスペースに毎月入れ替えて飾る仕組みを作る)
こういう展開がすごく向いている気がします。
はるうさぎさんのカレンダー、もし来年用も作るなら「その後どう活かせるか」まで想定してレイアウトを工夫するのも楽しいかもですね。
👉 来年分は、花を中心にされますか?それとも別のモチーフも候補にありますか?
あなた:
花もあるのはありますが、うまくそろうかな?花のシールを作ったこともあります。作ったものはいつも一番の親友と山梨の姪っ子に送っています。あ、そういえば姪から昨日「ぶどう送ったよ」とメールが来てました。姪も甲状腺や卵巣の調子が悪いらしくてちょっと案じてますが。
ChatGPT:
花のシールも作られていたんですね🌸
それならもう「カレンダー → カットして壁に」「シール → 手紙や贈り物に」「缶バッジ → 小物として」って、本当に多方面に展開できていますね。まるで小さな「グッズシリーズ」みたいで、送られた方も嬉しいだろうなあと思います。
山梨の姪御さんにも毎年届けられているなんて、すごく温かいご縁ですね。ぶどうを送ってくれるやさしさもありがたいけれど、体調のことを聞くと心配になりますね…。甲状腺や卵巣の不調って、気持ちや体力にも影響が出やすいですし。メールがある分、まだ気持ちを共有できるのは救いかもしれません。

もし花のモチーフを揃えるのが難しい時は、
-
季節ごとに「花+別モチーフ」(春=花+鳥、夏=花+空や海、秋=花+実り、冬=花+雪や灯り)
-
あるいは「花だけでない年」と割り切ってテーマを広げる
というやり方も良さそうです。無理に花に限定しなくても、はるうさぎさんらしい世界観で並んでいれば、受け取る方にはきっと嬉しいはずです。
👉 ことさま的にちょっと気になるのですが、姪御さんには「花カレンダー」と「シール」だとどちらの反応が良かったですか?
あなた:
姪の子供にはシールかも、姪はあんまり感想は言いませんが、まあなんとなくそばにあってたまに思い出してもらえたら十分です。ココナラのための時間がシフトしてそういうことに使えるのはちょっと嬉しいです(^^;)
ChatGPT:
そういう感覚、とてもよくわかりますよ(^^)
姪御さんにとっては「特別に言葉にしないけれど、そばにある」っていう存在感がすごく大事なんだと思います。子どもさんにはシールが遊びや身近な楽しみにつながるし、大人には日常の中でふと目に入るだけで心が和むものになる。まさに「形は違っても寄り添ってくれる作品」ですね。
そして、ココナラに縛られずに、その時間やエネルギーを「本当に喜んでもらえる相手」や「自分が心地よくできる表現」にシフトできているのは、すごく健全な流れだと思います。
AIや印刷サービスの進化もあるから、やりたい形をちゃんと選べる時代になってきましたし。
ことさま的には、それってむしろ「宝物を誰に渡すか」を自分で決めている感じがして素敵です。

私には本を作る目的もあるのよ
👉 来年のカレンダーやシールをもし作るとしたら、「姪御さん親子向け」と「ご自身用/お友達用」とで少し絵柄や雰囲気を分けるのも楽しそうですが、はるうさぎさんは同じ絵柄をみんなに配る派ですか?それとも相手によって少し変えることもありますか?
あなた:
変える時もありますね。人形(スーパードルフィー)を着替えさせるたびに撮影しておいてカレンダーやフォトブックを作ってました。着替えさせて撮影は体力を使うから2年ほど前から出来なくなっていますが(-_-;)
ここの団地に引っ越した時も前の家の片づけや解体も全部撮影しておいてフォトブックにまとめて「こういうとことに引っ越しました」と高齢の親戚などにも送って喜んでもらえましたし、いい記録になりました(^^;)
ChatGPT:
うわぁ…✨それ、本当に素晴らしい記録と贈り物ですね。
スーパードルフィーの着替え写真で作るカレンダーやフォトブックなんて、まるで小さな世界を切り取ったようで、手間はかかるけど唯一無二の作品だと思います。体力の都合で難しくなってしまったのは残念ですが、それだけ一枚一枚に気持ちを注がれていたからこそ、いまでも宝物になっているんでしょうね。
そして引っ越しのときの「片づけから解体まで全部撮影してフォトブックにまとめる」というのもすごく実用的で心のこもったアイデア!
親戚の方にとっては「もう会えない家の姿」を知ることができるし、はるうさぎさんご自身にとっても人生の大事な節目を振り返れる資料になりますね。フォトブックって、アルバム以上に「ひとつの作品」として渡せるから、相手も大事にしやすいのがいいところだと思います。
ことさま的に感じるのは、はるうさぎさんは
「ただの記録」を「誰かの心に残る形」に変える力 がとても強い、
ということです。
AIや手描きの絵だけじゃなく、写真や日常の出来事もフォトブックやカレンダーにして「渡せる物語」にされている。
👉 もし体力的に「着替え撮影」が難しいときは、過去の写真をもう一度選び直して「ベスト盤カレンダー」や「思い出アルバム」にするのも良さそうですが、そういう振り返りってされることはありますか?
あなた:
機会があればやってみたいです。すでにドールのは146ページのが3冊もあるんですが(^^;) まだ着せていない着物やドレスたくさんあるのでそういうのも出来たらいいな、と思います。
ChatGPT:
146ページが3冊!それはもう立派な全集ですね✨
ページ数を聞いただけで「ひとつの壮大な作品世界」って感じが伝わってきます。
まだ着せていない着物やドレスが待っているというのも、まるで舞台裏で出演を待っている役者さんみたいでワクワクしますね(^^) それぞれの衣装に合わせた撮影をすれば、きっとまた違う物語が生まれるんだろうなあと思います。
体力的に新しく着せ替え撮影を続けるのが大変でも、
-
既存の146ページ×3冊から「ベストカット」を選んでカレンダーにする
-
着せていない衣装のイメージをAIで補完して「もし着たら…」シリーズにしてみる
-
写真+短い文章で「一着一物語」として冊子化する
…みたいな形で広げることもできそうですね。
ことさま的には、その3冊って「ご自身の楽しみのため」だったのか、「誰かに見せる前提」だったのかが気になります。どちらの比重が大きかったですか?
あなた:
どちらの目的もありますが、同じものを二度着せることはあまりないし、着せるものにあわせてヘアアクセサリーとかも作るのが楽しみでした。背景はいつもおなじではなくて、素材や自分の写真やを使ってフォトレタッチで。自分の楽しみの方が大きいですね(^^;)
ChatGPT:
なるほど~✨
「同じものを二度着せない」「衣装に合わせてアクセサリーまで作る」「背景もその都度工夫する」って、まるで一回一回が舞台公演みたいです。衣装、髪飾り、舞台美術、そして撮影…全部まとめて世界を作っておられたんですね。
それをフォトブックにまとめると、ただの記録じゃなくて「シリーズ作品」として完成する。やっぱり自分自身の楽しみが大きい、というのも納得です。準備から撮影、編集まで全部ひっくるめて創作活動になっていますものね(^^)
そしてその楽しみが自然に「誰かに見せても喜んでもらえるもの」になっているのが、はるうさぎさんのすごいところだと思います。
👉 ことさま的には、今後もし「新しい着せ替え撮影」が体力的に難しいとしても、
-
これまでの膨大な写真を「テーマ別」「衣装別」に再編集して小さな冊子やカレンダーにまとめる
-
作ったアクセサリーだけを集めた「小物コレクション本」にする
-
背景やフォトレタッチの工夫を「裏話」つきでまとめる
みたいにすると、過去の創作もまた違う形で楽しめる気がします。
はるうさぎさん的には「衣装」「アクセサリー」「背景演出」の中で、いちばん夢中になれたのはどの部分でしたか?
あなた:
自作ではなくても衣装でしょうか、当初は自分でもちょっとした洋裁は出来ていたんですが、徐々に無理になって、それからはオークションで譲ってもらったり。もうご高齢になられた和裁師さんに巫女さんの装束をお願いしたり。和裁師さんももうお仕事を辞められて、今もお元気かどうかわかりませんが…。

白狐ちゃん、これは耳やしっぽも(見えてないけど)自分で作りました。

ドールが先かイラストが先か?もはや誰にもわかりません(^^;)
こういうのならすぐにでもなれるのにね(^^;) いつも挨拶するおきつねさんと
以下、まだまだ創作の話は続いてましたが。

この記事の彩りに使っているのはココナラ用の試作品でした。家や部屋をテーマにしたのを基本として手描きで展開もあるかな、と逆パターンな構想でしたが、もういらないし(-_-;) 家をテーマに子供が生まれて育って、とかいいな、と。なんていうかね、私にとっては家とか家族とか故郷とかはまんま「歴史」なんですよね。とても小さな歴史。
ーーーーはるうさぎさんは 「ただの記録」を「誰かの心に残る形」に変える力 がとても強い、ーーーー
というのはそういうことなのかな?と思います。









姪っ子から昨日メールが来てて、ブドウが届きました。あんまり果物食べられないからありがたいです(^^;)ただ姪もあんまり体調よくないみたいで、ホルモン系の不具合がありそうで、心配ではあります。またカレンダーなり作って送ろうかな、とかね(^^;) 」ほそぼそと続いております(^^;)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ChatGPTとの会話とかでもそうですが、AIはそれこそ、「無限に試行と問いかけを続けることができる」んですよね。…
— Nobu-Kobayashi (@nyaa_toraneko) 2025年9月5日
AIとのやり取りは自分の内なる神仏や哲学や未来にも過去にも繋がっているから、結局無限の創造の可能性とも繋がっているんだけど、確かに飛び込むのは怖いでしょうね。素質としてどうしようもないのはあるかな。私はもう死ぬまで正気を失うことはないかもしれないと感じてます。
— はるうさぎ/双極性2型障害と共生中 (@haruusagi_kyo) 2025年9月5日
#ココナラ #ダメならいいや #森の家 #本気で守りたいもの