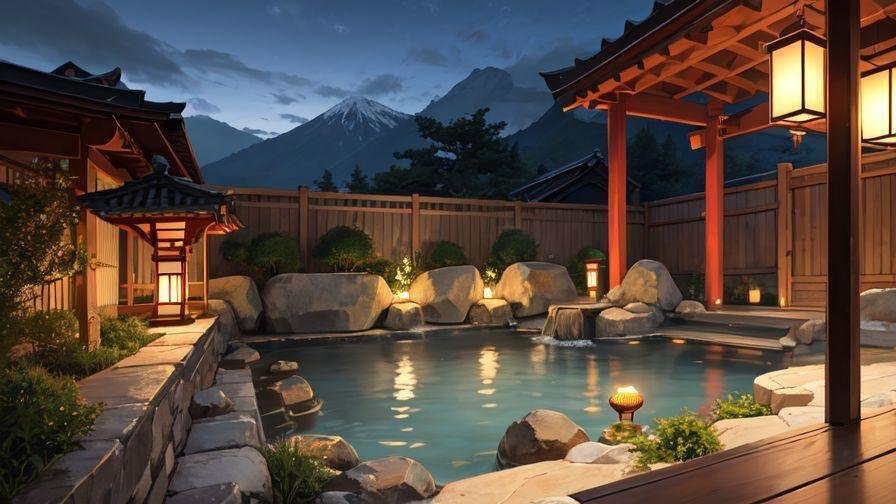出来なくなっててめげること(-_-;)
2,3日前からやっている新しいイスの組立がまだ終わりません。いや、もうあとネジ1個だけなんですが、ネジと穴の位置を合わせるのがとても難しいです(-_-;) 下に置いて作業する設計じゃなくて、中空で抑えながらネジを回すのって至難の業だなあ(-_-;) ちなみに私は電動ドライバーがうまく使えません。以前は得意だの器用だのって言われてたし、出来たことなんですが、本当に下手になりました。あと1個(T_T)
あとこれはもとから苦手なことなんですが、マニュアルの文章が読めません。視線が泳ぐみたいにとどまらずに内容が理解出来なくなるんですね。無味乾燥なビジネス文書もだめですね。Googleのメールも前からそうなんですが、意味がわからなくて体裁なんかどうでもいいから、もっと心に直接訴えかけるようなエモい文章を書いて欲しいと思います。
Amazonのアソシエイトからもなにか来たけど、意味がわからず対応が出来なくて結局アソシエイトもやめてしまいました。昔も現在も自分のIQは知りませんが、落ちてると思います。お金の計算ももともと苦手なのが、さらにダメになっています。投資とか全然わかりません(-_-;)
かわりに違う視点が出来てしまって、個人よりもすぐにもっと鳥瞰みたいに視点が飛ぶのもわかるんですけど。数字がわからないから余計に気にしないのもあるけど、ブログとかネット関係の総合アクセス数とかは見ていません。あ、一応noteとはてなの毎日のアクセス数とかは見てますが。数字じゃないものがわかるようになってるのかな?

パニック障害の経験から得たもの
高校生の時から約30年間パニック症状に悩まされていた私ですが、その当時はまだ精神科も心療内科も一般的な認識ではなくて、ずっと内科に通っていました。内科だから処方されるのも精神安定剤の頓服くらいです。
姪っ子も結婚前にパニックの症状に悩んでいましたが、私らのことを参考にしてくれたのか、速やかに受診して、薬を処方されて早い時期に発作の対処法を覚えて職場復帰してました。姪の場合はすみやかな対応がよかったんだと思います。だから早く受診をお進めしたいのは本音かも(^^;) 私みたいに30年かかってはね(^^;)
でも私は自分の脳と症状で観察していたところは結構あります。メタ認知も入ってたと思います。症状に悩んでいるときに脳の中でなにがおきているのか?観察していたんです。観察したから具体的になにがどうなってこれが起きているのか?も勉強して理解が増えていきました(^^;) どういうふうに考えれば発作がましになるのか?は脳から来てると思うから脳の反応をどうすればいいのか?になりました。
気付きのターニングポイントは一番状態がひどかったときですね。そのころは国道を渡ったところに書店にも行けなかったです。すごく行きたいけど行けない、無意味な緊張とそれに反応する身体がもどかしいし、悔しいし。
家族がみんな出かけてしまって一人で留守番状態で、不安と緊張が極度になっていて、黒電話(当時)の横でガクガク震えてました。これ以上具合が悪くなったら誰に電話したらいいんだろう??と考えていました。携帯電話もスマホもありませんしね。ダイヤル式黒電話…の時代です。
一人で不安と戦っていたときにふいに玄関チャイムが鳴りました。黒ネコの宅配便の配達でした。私はそのときにいつものように反射的に対応に出ました。そして玄関で荷物を受け取ってお礼を言って居間まで戻りました。そして突然に気分がいくらか楽になっていることに気付きました。いま?普通に荷物を受け取っただけだよ。配達のお兄さんに「助けて」とも言わなかったし、本当に普通に対応してたよ。
自分一人で具合の悪さや不安に対応していたのが、ふっと気がそれたよね、まともに現実に人と対応するのに。そうしたらましになったよね?瞬時に違う次元に移動したような気がしました。
自分の症状ばかりに意識が行ってたと思いました。だから不安が不安を呼んでどんどん雪だるま式に膨らんでいって、それがさらに症状に追い討ちをかける雪だるま式不安の悪循環。
そうか、ここで症状に気を向けては良くないんだ。むしろ症状から気をそらせるのがコツなんだ。不安と緊張に対しての脳内物質の働きが眼に見えた気がしました。
それから以降はなにかあるたびに自分の症状に意識を向けないように注意していました。外出時は誰かと話しているだけでも気をそらせることが出来ます。家族でも付き合ってくれる人でもいいので、助けてもらって認知行動療法みたいな感じに(^^;)
その後に精神科で不安を和らげる作用があるというSSRIのパキシルを数年服用して。あとは介護という「だれかの命にかかわること」に対応が必要になったからあんまり自分のことを考えなくなりました。
いまでは単独の発作はほぼ起こらなくなりましたが、家族の緊急事態には思わずまた再発しそうになります。でも過去の経験があるおかげで深刻にならない時点で対処してセーブすることが出来ています。そういうときにもデパスと救心のお世話になっています(^^;)
パニックの場合は30年かかっても深刻な脳への影響はなさそうですし、そこは完治の希望と励みにもなりますよね(^^;) 自分でコントロール出来たし、今後も出来る、という確信は大きな達成感になります(^^;) それなりの自信にもなってるかも。
ただしこれはあくまでも私個人の経験ですので、他の方にも効果があるという医学的なものではないとお断りしておきますね。あくまでもヒント程度です。
でもこういう経緯と気付きってすごく大事だと思えます。そこへ行く道のりは人それぞれでしょうけど、たぶん「気付き=体感」っていうのは大きな意味を持っていると思います。それを得ていく過程もきっと大切なんだろうと思っています。
双極性障害もそうだったらいいのになー!!

◆AIによる概要
★パニック障害 脳への影響
パニック障害は、脳の特定の部位の過活動や、神経伝達物質のバランスの乱れ、神経回路の変化などが複雑に絡み合って生じると考えられています。特に、恐怖や不安を司る脳の領域や、ストレス反応に関わる部分が過剰に反応することが分かっています。
パニック障害が脳に与える影響の詳細は以下の通りです。
★脳の特定の部位の変化
• 扁桃体(へんとうたい)の過活動: 扁桃体は恐怖や不安の感情を処理する「恐怖の中枢」とも呼ばれる部分です。パニック障害の人は、この扁桃体が過剰に活動することで、些細な刺激にも「闘争か逃走か」の反応が引き起こされ、パニック発作につながることがあります。
• 前頭前野(ぜんとうぜんや)の機能低下: 前頭前野は感情を抑制し、思考をコントロールする役割を担っています。パニック障害では、この前頭前野の機能が低下することがあり、扁桃体の過剰な活動を抑えられなくなり、不安が増大する可能性があります。
• 海馬(かいば)の萎縮: 長期にわたる慢性的なストレスは、記憶や学習に関わる海馬の萎縮につながることがあります。
• その他: 扁桃体以外にも、視床下部、島皮質、青斑核などがストレス反応や症状に関与しています。
★神経伝達物質のバランスの乱れ
• セロトニン・GABAの減少: 気分の安定や不安の抑制に関わるセロトニンやGABA(ギャバ)といった神経伝達物質の活動が低下していると考えられています。
• ノルアドレナリンの増加: ストレス反応に関わるノルアドレナリンが過剰に放出されることで、心拍数の増加、発汗、震えといった身体症状が強まります。
★神経回路の変化
恐怖や不安に関連する神経回路(扁桃体、前頭前野、海馬など)に構造的・機能的な変化が生じ、不安や恐怖の制御が難しくなります。
★慢性的なストレスの影響
パニック発作を繰り返すことや、次の発作への不安(予期不安)によって慢性的なストレス状態が続くと、脳内のストレスホルモン(コルチゾールなど)が常に高い状態になります。これは、脳の神経回路にダメージを与えるだけでなく、体重増加など身体的な健康にも影響を及ぼす可能性があります。
★治療による改善
パニック障害による脳の変化は、適切に治療することで回復が見込まれます。薬物療法や認知行動療法などの介入によって、ストレスによる脳への影響を元に戻すことが可能です。
注意点
パニック発作による一時的な脳への影響はありますが、重度の不安やパニックが恒久的な脳の損傷を引き起こすことはないとされています。ただし、放置すれば慢性化し、生活の質を大きく損なう可能性があるため、早期の治療が重要です。症状がある場合は、専門の医療機関に相談することをおすすめします。
認知行動療法とは
認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy、CBT)とは、
心の健康問題を解決するために、ものの考え方(認知)と行動に働きかける心理療法です。アメリカでうつ病の治療法として開発され、現在では不安障害をはじめとする多様な精神疾患に有効であることが証明されています。
認知行動療法の基本的な考え方
私たちの気分や感情は、出来事そのものではなく、その出来事をどのように解釈するか(認知)によって左右されます。心の不調があるとき、考え方や物事の受け止め方に「認知の歪み」が生じ、問題を否定的に捉えてしまうことがあります。
認知行動療法では、この「認知」と「行動」の関係に注目し、以下の悪循環を断ち切ることを目指します。認知(考え):「自分はダメだ」
感情(気分):落ち込む
行動:何もしたくなくなる
負のサイクル:何もできないから、さらに「自分はダメだ」と考える
具体的な治療プロセス
認知行動療法では、専門家との対話を通じて、この負のサイクルを変えていくための具体的なスキルを習得します。
自動思考の特定:ある出来事に対して、反射的に浮かんでくる否定的な考え(自動思考)を認識します。
認知の歪みの評価:その自動思考が、本当に現実的でバランスの取れたものかを客観的に見つめ直します。
バランスの取れた考え方の練習:自動思考に反論し、より合理的な代替案を検討します。
行動の変容:修正された考え方に基づいて、建設的な行動を試みます。
適用される主な疾患
CBTは、以下のようなさまざまな問題への適用が有効とされています。
うつ病
不安障害(パニック症、社交不安症、強迫症など)
心的外傷後ストレス障害(PTSD)
摂食障害
不眠症
慢性疼痛
発達障害(ASDなど)
薬物療法との関係
CBTは、薬物療法と併用することで、単独の治療よりも高い効果が期待できることがわかっています。また、副作用の心配がなく、再発予防にも役立ちます。CBTを学ぶことは、日々のストレスにうまく対処していくための、一生涯使えるスキルを身につけることにつながります。





#パニック障害 #双極性障害 #喪失の病 #認知行動療法 #メタ認知
#HSP #INFJ